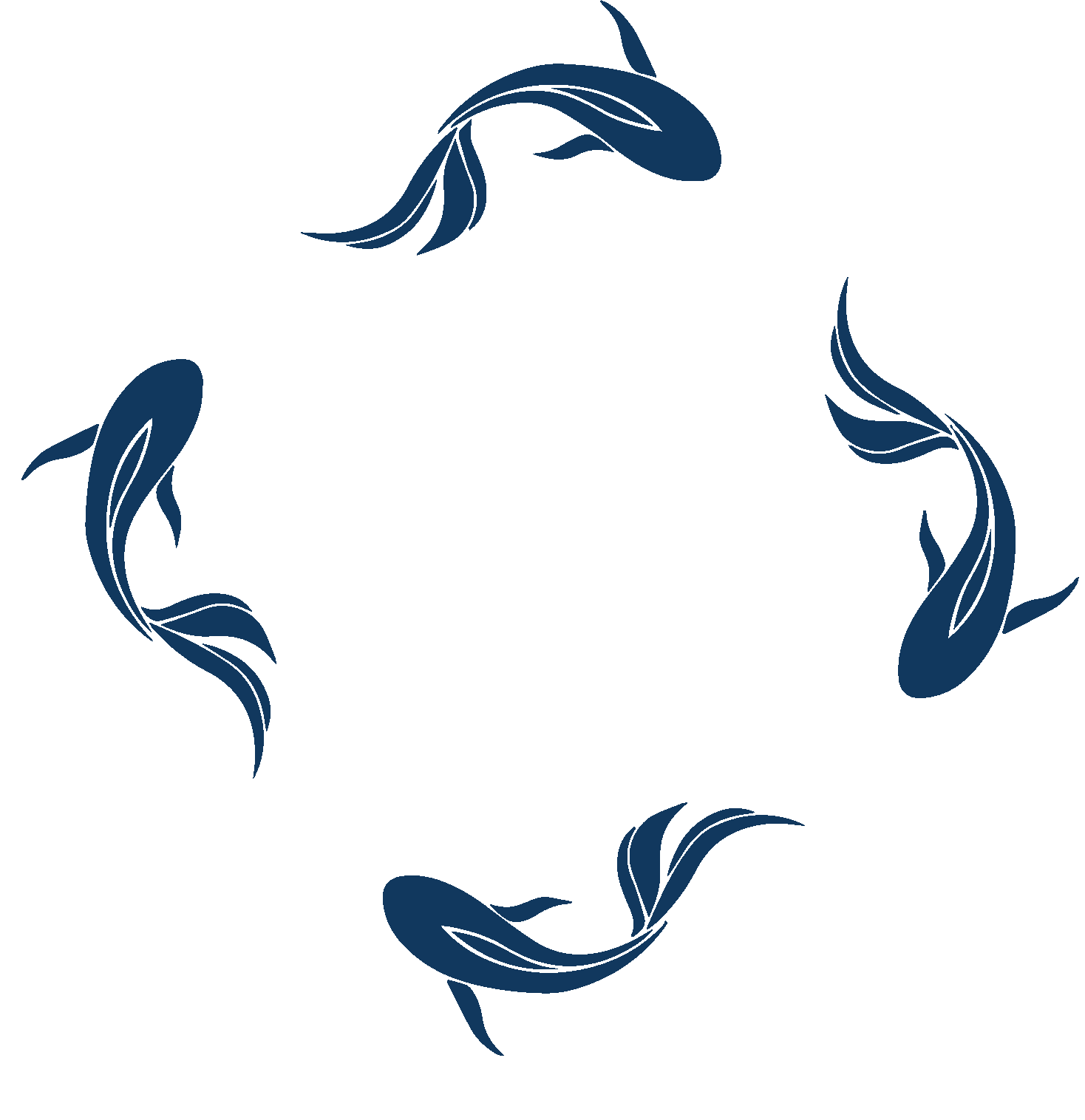こんがりと、こんなに肌が焼けたのはいつぶりだろうか。
太陽を追うように、3週間かけてヨーロッパ各地──パリ、リスボン、プーリア、フィレンツェ、そしてマヨルカ島を巡った。
南イタリアのプーリアでは、出産を控えた友人に会いに。この“イタリアのかかと”にあたる土地には、60億本とも言われるオリーブの木が広がっている。

何もしないで、ただ海を眺め、潮風に頬をさらしながら、友人と過ごした時間。これまで一緒に作ってきた思い出を振り返りながら、その静けさと穏やかさがとても贅沢に感じられた。もうすぐ生まれる新しい命とともに、これからの20年、彼女の景色はきっと大きく変わっていくのだろう。そんな未来を、ほんの少し想像させてもらった。
リスボンでは、人生初の一人旅。灼熱の太陽をサングラス越しに浴びながら、石畳の路地を歩き、タイルアートや黄色いケーブルカーを眺める。不思議と、初めて訪れたのにどこか懐かしい。夕暮れのアルファマ地区では、ギターの音に惹かれてベンチに腰かけ、一人で音に耳を澄ませた。

そして、フィレンツェ。美しいものを観て、美しいものを学ぶ街。ジュエリーショップを巡りながら、ウフィツィ美術館ではボッティチェリの《春》や《ヴィーナスの誕生》の前で立ち尽くし、ミケランジェロのダビデ像の傑作を前に言葉を失う。大人になった今、芸術と歴史が胸に深く染み渡っていくのを感じる。
マンハッタンのカオスから離れ、時間の流れがまったく異なる場所へ。
いつからだろう、「休む」ことに罪悪感を覚えるようになったのは。
学生時代から、ハムスターのように、歯車の中で何かに追われるように動き続けていた。経営者という立場になってからはなおさら、「止まること」は“もったいない”と感じ、まだ未熟だからこそ動き続けなければと思っていた。それは、家族を養うためにがむしゃらに働く母の背中を、ずっと見てきたからかもしれない。
でも、気づいた。
クリエイターという生き方には、きっと“完全な休み”なんて存在しないのだと。見るもの、聴くもの、触れるもの──すべてがインスピレーションになる。
脳は、たしかにいつもどこかで動き続けている。
マヨルカ島で、親友との二人旅。

車で島を一周し、すべてのビーチを巡り、海沿いのテラスでパエリアを味わいながら、お互いの軌跡とこれからの野望を語り合う。
沈む夕日が朱に染まり、空と海を神々しく照らすその光。助手席に座る自分は、頬をなでる風を感じながら、思考を巡らせていた。
地中海に身を預け、波に漂い、ミラモアのデュオチェーンとイタリアで手に入れたピアスがカチカチと響き、海の音と混ざり合う。空と海が一体化するような青に溶込み、自分がこの世界のほんの“点”のような存在だと気づかされた。抱えていた悩みなんて、実にちっぽけなものだと悟る。
塩水に濡れた髪を指で梳かしながら、太陽の光がミラモアのジュエリーに反射して輝くのを見て、「自分のデザインが好きだ」と頷いた。その素直な感覚こそ、今の自分に必要だった。
「そのジュエリー、どこの?」と、旅の途中、何人もの人に声をかけられた。そのたびに自分のデザイン哲学を語り、気づけば人生について何時間も語り合っていた。名前も知らないその人との会話が、ニューヨークではありえないことだからこそ、あえて楽しんでみた。
「あなたって、太陽みたいなオーラをまとってるのね。つい、声をかけたくなったの」と。
彼女の手にはパウロ・コエーリョの『アルケミスト』。スペインからエジプトへ旅をする少年が、“前兆(オーメン)”を辿りながら、最終的に宝物は外ではなく、自分の内側にあると気づく物語。
「君こそが、僕へのサインだったのかもしれないね」と、僕はポツリとつぶやいた。帰りの機内でその本を一気に読み、登場する少年と自分が重なった。かつての少年だった自分に、初めて「よく頑張ってるよ」と声をかけてみた。
大人になっても、夢を信じて動き続けていい。

と。「これでいい」ではなく、「これがいい」この夏は、自分の“内側”という名の宝物を見つけるための、ひたすら“オーメン”が導く、予想外の旅となった。そのおかげで、少しだけ、自分に優しくなれた気がする。
ああ、たのしかった。
稲木ジョージ
ミラモア創設者&金継ぎ哲学者