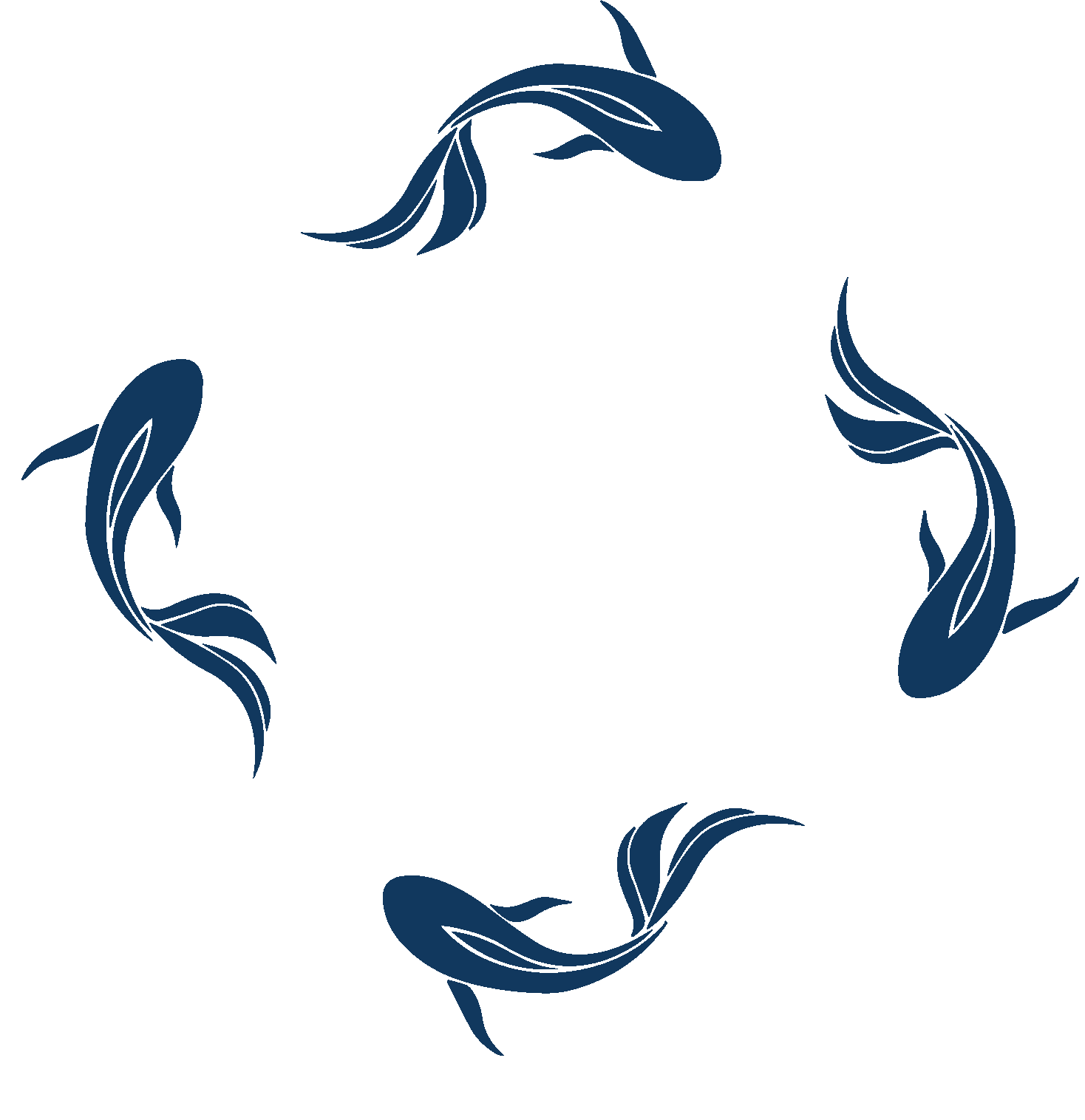「物柄(ものがら)」という言葉がある。人や物、事柄が本来持っている性質や背景、成り立ちを指す。現代ではあまり耳にしない、古風な日本語。
その言葉を初めて聞いたのは、茶筒ブランド・開化堂の6代目、八木隆裕さんと工芸の話をしていたときだった。ふとした会話のなかで、その響きが不思議と耳に残った。
中世から近世――鎌倉から江戸のあたりには、すでに使われていたという。
置き換えるなら「性格」「背景」「立場」「状況」…がある。けれど本当は、そんな言葉ではすくいきれない何か。
「人柄」という言葉が浮かび、意味だけでなく、音の奥にも、深く静かな余韻が残った。
“物に魂が宿る”とは、どういうことなのだろう。
作り手の意志が入り込むこと?あるいは、知らぬ間に滲み出てしまうものなのか。
お互いモノづくりに携わっているからこそ、八木さんとの対話は自然とそんな問いを導いてくれた。
自分は、「物柄」のある作品を、作れているのだろうか?

出会いは、2024年の秋。京都で開催されたイベントに訪れたとき、共通の友人を通じて紹介された。メガネの奥に見えた大きな目と、清々しい笑顔が印象的だった。
そのご縁から、京都のアトリエを見学させてもらえることに。150年という時間をつないできた空間で、八木さんは語ってくれた。
戦時中、お祖父様が道具を必死に守り抜いたこと。どんな時代であっても、変わらないものを作り続けるということ。
その瞬間、今の世界情勢が頭をよぎる。
戦争を生き抜き、時代の変化を乗り越えながらも、変わらぬ茶筒を作り続けてきたという事実。
アーカイブに残された茶筒は、同じように見えて、微妙に表情が違う。
それがまさに、「物柄」だと感じさせられた。

アトリエの片隅で、目に留まったものがある。無数の錆びたピン。
茶筒の側面を留めるための、開化堂独自の道具だという。
「挟む(はさむ)」という言葉が訛って、「ハソ」や「ハッソウ」と呼ばれているらしい。
そのピンが、なぜか光って見えた。もしくは、こちらに気づいて――“僕たちに見つけてほしかった”と言わんばかりに、光っていたのかもしれない。
あまりにもハッソに感動していた僕を、八木さんは少し不思議そうな表情で見ながら、それでも快く、錆びた一本を譲ってくださった。
手から手へ、渡されるインスピレーション。
ちょうどその頃、アトリエ長と「新しいチェーンを作りたいね」と話していたタイミングだった。
偶然のようで、どこか必然のような流れ。気持ちが熱いうちに、すぐにアトリエ長に伝えた。
いつも通りの、僕の無茶ぶり。そして、それをさらりと超えてくるのが、アトリエ長。
ミラモアらしいチェーン。ジョージらしい発想。ジュエリーは一生もの。
飽きがこないこと。でも、ちゃんと遊び心があること。
奇抜なものを作るのは、実は簡単だ。
でも、シンプルを極めるのは難しい。シンプルすぎても芸がないし、複雑すぎてもケバくなる。
そんなミーティングを繰り返すなかで、アトリエ長がつぶやいた。
「知恵の輪みたいに、コマをつなげたい。」
自分の無茶ぶりに、さらに無茶ぶりを重ねてくれる。これが、僕とアトリエ長の最強タグの秘密だ。
構想は一気に動き出した。素材には、ミラモアとしては初めてとなるシルバーを採用。
ただし、シルバーは柔らかく、知恵の輪のような構造には向いていない。
コマひとつひとつに“取り外せる仕組み”を組み込むには、強度をどう確保するかが最大の課題だった。
そこでアトリエ長が選んだのが、「時効硬化」という技法。
なんと、自家用ピザ窯でシルバーを300℃に加熱し、ゆっくり冷ますというプロセスで硬度を高める。
料理が趣味の彼らしい発想に、思わず笑みがこぼれた。
想像してみる。ミラモアの新作のために、夜な夜なピザ窯でシルバーを焼いているアトリエ長の姿。
一生懸命で、お茶目で。なんだか嬉しくなった。
試行錯誤しながらも、このプロセスを通じてシルバーは必要な強度を得ることができた。
それだけではなく、時効硬化したことでシルバーが日常にも耐えられる、傷がつきにくいタフさも備えることができた。
完成したチェーンには、18金のボールとダイヤモンドがアクセントとして組み込まれている。
一見ごつく見えるのに、肌にあたると驚くほど滑らか。どの角度から見ても、美しいラインが続く。

「ミラモアらしさ」はそのままに、まったく新しいフォルムが生まれた。
撮影は、開化堂のアトリエで行った。八木さんとの特別な対談、アトリエ長の初インタビューも記録に残した。
こうして誕生したのが、HASSOUパズルチェーン。
そこには確かに、「物柄」を宿らせた。
人柄が導いた偶然とご縁が、数珠つなぎになってたどり着いた、新しい“物”。
永く残っていくデザインになれたら、嬉しい。